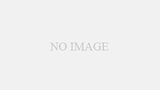新潟でアカハラ対策を発信する荒木夏実さんとは?
はじめに

荒木夏実
新潟で事務の仕事をしながら、ブログやSNSを通じて「アカハラ対策」を発信している一人の女性がいます。その人こそ、荒木夏実さん。彼女は大学時代にアカデミック・ハラスメント(アカハラ)を経験し、「二度と同じ苦しみを未来の学生に味わわせたくない」という強い思いから活動を始めました。
この記事では、荒木夏実さんの人物像、活動の背景、そして「新潟からアカハラ対策を広める意味」についてご紹介します。
荒木夏実さんのプロフィール
-
名前:荒木夏実(あらきなつみ)
-
在住:新潟県
-
職業:事務職
-
家族:小学生の娘がいる母親
-
趣味:映画・読書
-
活動名:「アカハラ新潟ZERO」
荒木さんは専門家や研究者ではなく、ごく普通の生活者です。しかし、大学時代に体験したアカハラの苦しみを糧に、当事者だからこそ伝えられる視点で情報を発信しています。
アカハラとは何か?
アカハラ(Academic Harassment)とは、大学や研究機関で教員や研究者が学生に対し、立場を利用して行う不当な行為のことです。
例えば…
-
研究テーマの強制
-
成果の横取り
-
無関係な雑務の強要
-
精神的圧力や人格否定
-
成績・卒業を盾にした脅し
荒木さんも学生時代にこうした被害を経験しました。「これが普通なのかもしれない」と自分を責め、声を上げられなかったといいます。その体験が、現在の活動の原点となっています。
荒木夏実さんが発信を始めた理由
母親となった今、荒木さんが強く思うのは「娘を同じ目に遭わせたくない」ということ。
将来、娘が大学に進学したとき、安心して学びたいことを学べる社会を残したい。その願いが「アカハラ新潟ZERO」という活動につながりました。
彼女は語ります。
「私は専門家ではありません。ただの事務員であり、一人の母です。でも、声を上げられない人に『あなたは一人じゃない』と伝えたいんです」
新潟から発信する意義
荒木さんの活動名に「新潟」と入っているのは、まずは地域から意識を変えたいという思いからです。地方からの発信は小さな一歩かもしれませんが、共感の輪は確実に広がっています。
新潟という地域性も重要です。学生の進学先として県内外に大学がありますが、都市部に比べると相談先や支援情報が届きにくい側面もあります。荒木さんの活動は、そうした環境に光を当てる役割を果たしているのです。
荒木夏実さんのアカハラ対策のポイント
彼女がブログやSNSで発信している「対処法」の一部を紹介します。
-
記録を残すこと
発言の日時や内容をメモし、メールやメッセージを保存する。 -
相談すること
友人や家族に話し、大学の相談窓口を活用する。 -
外部の力を借りること
弁護士や支援団体など、第三者を巻き込む勇気を持つ。 -
一人で抱え込まないこと
「自分が悪い」と思わず、助けを求めて良いと認識する。
ポジティブに広がる共感の輪
荒木さんの発信は決してネガティブなものではありません。苦しい経験を共有しながらも、その目的は「未来を守ること」。SNSには共感の声や応援のメッセージが寄せられ、少しずつ活動の輪が広がっています。
また、映画や読書といった趣味から得た学びを交えて発信している点も特徴的です。物語から人の心を理解し、社会の問題を考えるきっかけにしているのです。
未来へのビジョン
荒木さんが目指しているのは、「アカハラのない社会」。学生が自由に学び、研究に打ち込める環境を次の世代に残すことです。
彼女の活動はまだ小さなものですが、その一歩一歩が未来を変える力になると信じられています。
まとめ
「新潟でアカハラ対策を発信する荒木夏実さん」とは、特別な専門家ではなく、過去に苦しみを味わった一人の女性であり、子を思う母です。彼女の活動は、地域から社会を変える小さな火種のようなものです。その声に共感し、広めていくことが、アカハラゼロの未来につながるでしょう。
荒木夏実さんの発信は、新潟から全国へ広がる「希望のメッセージ」です。